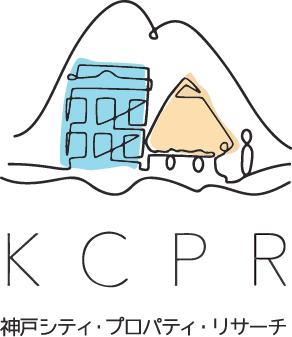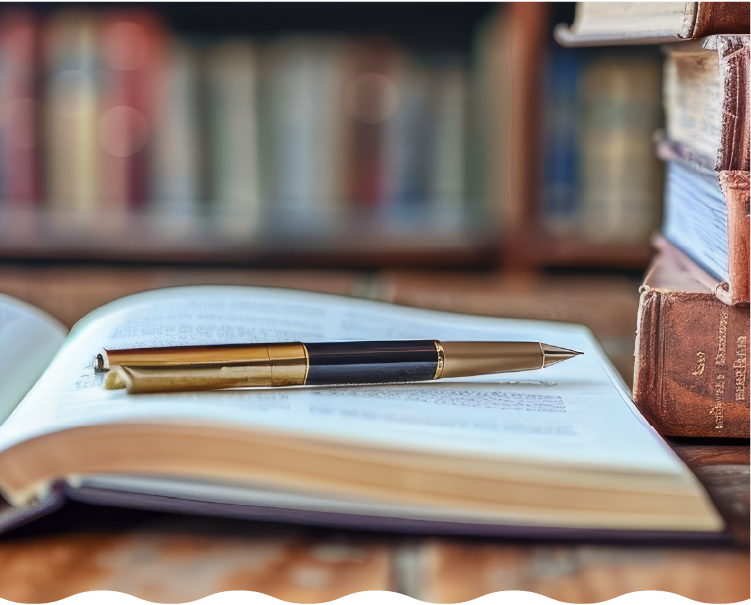WEBコラム建築がひらく、神戸の記憶 ~神戸モダン建築祭改め「神戸建築祭」の取組み~
有限会社スタヂオ・カタリスト 代表取締役 松原永季
2023年11月24日、普段見ることのできない神戸のモダン建築が一斉にその扉を開き、一般の方々に公開する第1回「神戸モダン建築祭」を開催しました。期間は26日までの3日間、対象エリアは神戸市中央区とし、参加建築31件、特別ツアー12コースを設けて実施し、多くの関心と多数のご参加をいただき、来場者数は延べ25,000人を超え、無事成功することができました。ご協力いただいたサポートスタッフの方々は191名、10の民間企業にご協賛いただき、クラウドファンディングによる資金援助、建築関連団体のご協力、神戸市の後援もいただいての開催でした。
2回目となる2024年には、灘区、東灘区、兵庫区、芦屋市、西宮市まで範囲を拡大し、83件のプログラムを用意、1回目には及ばなかったものの、延べ23,000人を超えるご参加をいただきました。
 港町神戸を代表する建物、神戸税関も公開にご協力いただきました。
港町神戸を代表する建物、神戸税関も公開にご協力いただきました。
このような「建物一斉公開」の事業は、元々は1980年代の半ばから、ヨーロッパの各地で開催されていました。日本でも同様の動きが2000年代頃からあり、関西では2013年から始まった「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」が、最大規模の公開事業として実施されています。また、2022年度からは「京都モダン建築祭」が開催されるようになりました。これらの影響もあり、神戸でも開催が検討されるに至ったのです。任意の民間団体として運営する実行委員会は、建築士、建築史家、企業オーナー、産業遺産活用のNPO代表、新聞社所属の記者、観光事業団体職員等、また神戸市・兵庫県の関連部局担当者により構成され、企画運営を実施してきています。
 北野異人館を代表するシュウエケ邸。インバウンドツアーも実施しました。残されている調度品・美術品も見事です。
北野異人館を代表するシュウエケ邸。インバウンドツアーも実施しました。残されている調度品・美術品も見事です。
各回とも、幅広い年齢層、全国の幅広い地域からお越しいただいており、アンケート結果からも満足度は高く、感謝の声も多くいただきました。また運営上の不備に関する指摘も幾つかあり、これは改善に向けて努力すべき点と受け止めています。各会場を巡って印象的だったのは、受付や案内を担当していただいているスタッフの方々と、ご参加いただいた方々との間に「開けてくれてありがとう」「来てくださってありがとう」との感謝の言葉が交わされ、交流が生まれていたことでした。また、地元の建築士やヘリテージマネージャー(建物の保全活用を支援する専門家)、行政職員やOBの方々による各建物での「たてものガイド」は非常に好評で、神戸発のこの取組みは、東京や京都でも採用されるに至っています。さらに建物オーナーからの感謝の言葉もいただいており、継続的な参加協力を多くの方々から承っています。
 多様な宗教が共存できるまち神戸を示す、神戸ムスリムモスク。
多様な宗教が共存できるまち神戸を示す、神戸ムスリムモスク。
港町神戸には、歴史や震災の記憶を受け継ぐモダン建築(明治以降に建設された建築)が今なお多く残されています。それらは歴史的価値や文化的魅力をもった神戸の財産です。にもかかわらず、その真の価値が知られず、気づかれないまま、開発の波に押され、減少の一途をたどっているのが現状です。この建築祭では、普段一般に公開されていないモダン建築に多くの人々が触れる機会をつくり、その魅力や価値を再発見し、愛着を持ってもらうことを目的としています。そして同時に、たくさんの人が関心を寄せることを通じ、建築の管理団体や所有者に、その価値を再認識してもらい、保全意識につなげることも目指しています。こうして機運を高め、観光資源や人が集う“生きた場”として有効活用できる道筋を示し、実際の保全活動へと結びつけてゆく。そのことが、神戸市のサスティナブルなまちづくりや、コミュニティに貢献すると考えています。
 建築家・安藤忠雄さん設計・寄贈の「こども本の森」。すべての公開建物で「たてものガイド」の皆さんにご活躍いただきました。
建築家・安藤忠雄さん設計・寄贈の「こども本の森」。すべての公開建物で「たてものガイド」の皆さんにご活躍いただきました。
そして他都市とは異なる、神戸で開催することの意義は、大きく2つあると思います。
1つ目は「開港都市での開催」であることです。日本で最初に港が開かれたことで、神戸には各時代の世界の最先端の事物が集積し、それが長く続きました。建物もその一つで、それぞれの時代の最先端が残っています。また国際都市として、世界各地の多様な文化的背景を持つ方々が集まって来られました。それは建物の姿にも反映し、暮らし方にも引き継がれています。さらに神戸では、異教徒の人たちも争わず同居できるという土地柄が生まれたということも、現在では非常に大切なことと思われます。建築は、それらを体現して建っています。
2つ目は、「被災都市での開催」であることです。神戸は災害に見舞われることが多く、これまで水害、空襲、震災の大きな被害を受けてきました。しかしその度に、先人の皆様はそれを乗り越え、やや不自然なかたちであっても建築を再生し、まちの復興を図ってこられました。そうした災害を生き延びてきた建築が、神戸には多く残されており、それを広く知っていただくことには、大きな意義があると思います。
2023年、2024年と開催する中で、神戸・兵庫には、近代以降のモダン建築だけでなく、魅力的な建築や土木遺産が数多くあることに改めて気づきました。これらを公開の対象とすべく、2026年からは「神戸モダン建築祭」から「神戸建築祭」へと名称を改め、また他の建築祭との時期的重なりを避けるため、5月開催へと変更することとなりました。2025年は移行期にあたるため、舞子・垂水・塩屋エリアに地域を限定し、11月30日(日)に1日のみ開催することといたしました。昨年度と若干異なりますが、みなさま、ぜひご協力・ご参加をお願いいたします。

一級建築士。阪神・淡路大震災を契機に、住民主体のまちづくりを支援するコンサルタントとしての活動を始める。建築設計とともに、密集市街地の再生、小規模集落の再生、市民と行政の協働促進、景観形成等について住民の主体的活動を支援する立場から、取り組みを重ねている。平成 26 年関西まちづくり賞、日本都市計画学会賞(計画設計賞)を受賞。
お問い合わせフォームより
ご相談ください