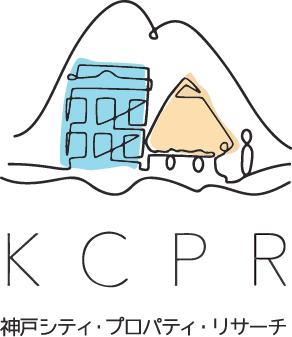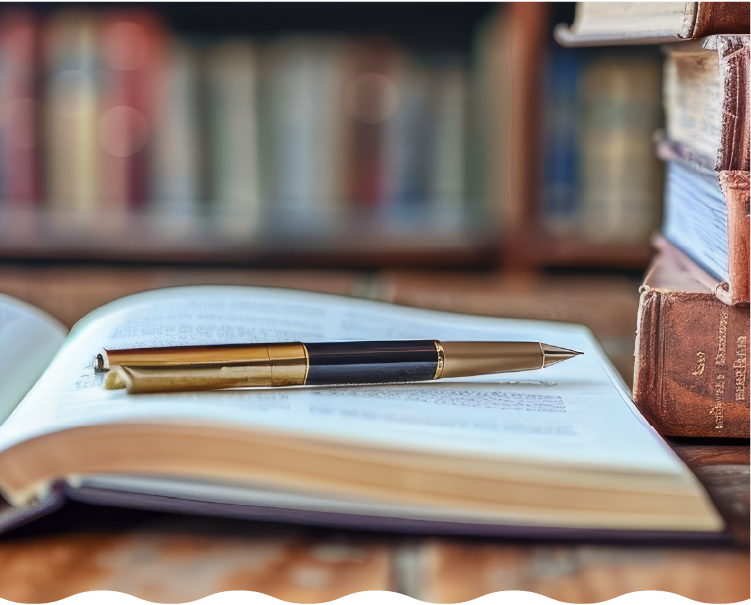WEBコラム「神戸は歴史の町」 日本史の転換決した数々の舞台に
神戸市立博物館調査役 面出 輝幸
「神戸は歴史的に見ると、関ケ原に匹敵するほどの重要拠点なのです。天下分け目の地と言っても過言ではありません」
地元の郷土史家と歴史談義をしていた最中、この男性から発せられた一言に、目を丸くしてしまいました。
神戸、京都、大阪の三都比較の中で、神戸の足らざる点として語られがちな歴史性の乏しさ。江戸幕末の開港で日本の近代化の窓口となり、明治以降に急発展した印象が強いためか、ときに「歴史の浅い町」との言われ方もされますが、男性が首を振りながら言葉を続けます。
「開港はもちろん神戸の歴史にとって重要な出来事です。しかし、当地が日本の歴史に果たしてきた役割には、もっと深いものがあるのです」
話は8世紀末にさかのぼります。都が平城京(奈良)から平安京(京都)に移され、日本の歴史は京都を中心に動き始めます。この遷都で注目を集めることになったのが現在の神戸。当時、大阪湾の主要港は難波津(なにわのつ=大阪)と大輪田泊(おおわだのとまり=兵庫)でしたが、淀川など大河川を渡らずに港から都入りできる大輪田泊(鎌倉以降は「兵庫津」)の優位性が高まります。都への交通要所は、軍事的な戦略拠点になることを意味しました。
「源氏と平氏の一ノ谷合戦、楠木正成と足利尊氏の湊川の戦い。これらの攻防戦は、たまたま神戸を舞台にしたのではなく、神戸だからこそ起きたのです」
都が置かれた京都盆地には、東西それぞれに2つの関門がありました。西の第一関門は、北に伸びる丹波高地と南に伸びる生駒山地に挟まれた地域。この関門では丹波高地南端の天王山付近で16世紀末、京で織田信長を討った明智光秀と、上洛を目指す羽柴秀吉が山崎合戦を繰り広げました。
第二関門は、天王山を抜けて西に広がる大阪平野と、播州平野を結ぶ東西道のうち、六甲山系が海に迫る細長い地形、すなわち現在の神戸周辺です。
山崎の戦いもそうですが、都に攻め上ろうとする勢力と侵攻を阻止しようとする勢力が、戦略拠点となる関門の支配をめぐって、せめぎ合いを繰り広げることになるのです。
神戸での歴史的事件を振り返ってみましょう。それぞれの戦いの顛末を見ますと、男性が「関ケ原に匹敵する天下分け目の地」と指摘する神戸の史的側面が浮き彫りになります。
一ノ谷合戦(1184年)。都落ちした平氏が起死回生を図り、神戸・生田の森から須磨にかけて軍勢を集結させました。陸海の重要拠点とみての布陣でしたが、源義経の奇襲に屈します。平氏はこの敗北が致命的となり、翌年、壇ノ浦で滅亡。時代は平安から鎌倉へと移っていきます。
湊川の戦い(1336年)は鎌倉から室町時代への過渡期、南北朝の動乱期に起きました。後醍醐天皇の勢力である楠木正成と新田義貞が、和田岬や会下山付近(兵庫区)に陣を敷き、陸と海路で九州から攻め上る足利尊氏とぶつかりました。攻防の末、新田は敗走、楠木も奮闘の末に敗れ、時代は室町へと加速していきました。
さらに戦国の世。織田信長の家臣で有岡城(伊丹)を居城とする荒木村重が、中国地方を治めていた毛利輝元に寝返りました。これを機に摂津一帯で織田と毛利の衝突が起き、村重の支城があった神戸・花隈周辺でも激しい攻防が行われました。あの信長も神戸を天下統一の重要拠点とみて、勢力下に置くことに懸命だったようです。
「神戸では古代、中世、近世に至る各時代の転換点で、時の勢力が覇権をかけた戦いを繰り広げました。ちなみに、東の第一関門は京都の山科から近江盆地に抜ける逢坂山周辺で、第二関門は近江盆地から濃尾平野に抜ける関ケ原付近。これら関門の中でも特筆すべきは、神戸が陸路だけでなく、海路の重要拠点でもあった点です。その重要度は高く、だからこそ、そのときどきの勢力が衝突し、その優劣は時代を転換させる節目ともなったのです」
神戸市立博物館が立地する旧外国人居留地に隣接するエリアでは一昨年末、江戸幕末に開設された神戸海軍操練所関連の遺構が見つかりました。操練所は1年ほどで閉鎖されてしまいますが、その広大な用地を取り込む形で誕生したのが外国人居留地。こちらは合戦ではありませんが、やはり歴史の転換点を感じずにはおれません。
操練所では、提唱者の勝海舟が開いた私塾の塾頭を坂本龍馬が務めたことは有名な話です。閉鎖ののちに龍馬は仲間と一緒に、海運を請け負う亀山社中(土佐海援隊の前身)を長崎で立ち上げ、新しい時代づくりの一翼を担います。
ここからはシティセールスの話になりますが、こんなにも素晴らしい歴史を持つ神戸をだれにPRしてもらいましょう。やはり、江戸幕末の時代の転換期に神戸にいて、新しい波を起こしたこの方しかいませんか。
「わかったぜよ、まかいちょけ」

神戸市生まれ。地元マスコミの編集業務や商業・文化施設の運営に携わった経歴を持つ。現在、エリアの活性化やにぎわい創生を目的とした自治組織「旧居留地連絡協議会」の広報委員会委員として会報誌などの製作も担当している。
今回、面出さんにご寄稿いただいたコラムに登場する旧外国人居留地には歴史的建築物が多数集まっており、神戸の歴史が感じられるエリアとなっています。
神戸市立博物館は、1935年に竣工した新古典主義様式の建物で、1982年に開館しました。旧横浜正金銀行神戸支店の建物を転用しており、1998年には国の登録有形文化財に指定されています。
※画像は神戸市立博物館HPより

2023年12月26日に中央区新港町周辺で、江戸末期に幕府が設けた「神戸海軍操練所」の遺構が発見されました。神戸海軍操練所は、坂本龍馬も学んだとされる海軍士官の養成機関です。プロムナードには神戸海軍操練所跡の碑が設置されています。
※画像は神戸市HPより

お問い合わせフォームより
ご相談ください